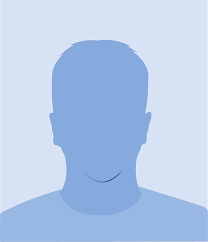|
所属 |
農学部 農学部門海洋生命科学領域 |
|
職名 |
教授 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Kishi D., Johnson K.G., Fukami H.
Zoologica Scripta 0 1 - 19 2025年11月
担当区分:責任著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Zoologica Scripta
The species-level identification of zooxanthellate scleractinian corals based on morphology is extremely difficult. This difficulty can potentially lead to inaccurate conclusions due to species misidentification, posing a risk in applied research. In this study, we integrated detailed morphological and molecular phylogenetic analyses to investigate the hidden morphological polymorphisms of Favites valenciennesii, a species primarily characterised by the presence of groove-and-tube structures between corallites. Because F. valenciennesii shares morphological similarities with related taxa, its taxonomic status has remained unresolved for over 170 years. To address this, we combined Random Forest-based feature selection with multivariate analysis to identify species-specific morphological characteristics of F. valenciennesii. This approach classified F. valenciennesii into four morphologically distinct types (types A–D). Molecular phylogenetic analysis further revealed that two types (A and B) belong to the genus Favites, while the other two types (C and D) belong to Dipsastraea. Within Favites, two distinct clades corresponded to types A and B. Comparison with type specimens and taxonomic studies confirmed that type A represented true F. valenciennesii, while type B represented Favites irregularis comb. nov. Although types C and D were not formally described, the results suggested that they likely represent undescribed species of Dipsastraea. The integrated approach used in this study provides highly accurate species identification and offers significant potential for improving coral taxonomy.
DOI: 10.1111/zsc.70033
-
Northernmost official record of Acropora cf. solitaryensis and A. aff. divaricata colonies landed at Sajima Fishing Port, Yokosuka City, Kanagawa Prefecture 査読あり
Nami Okubo, Nobuhisa Iwasaki, Soranoshin Kodama, Hiroaki Ishiyama, Hironobu Fukami
Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 27 ( 1 ) 218 - 221 2025年12月
担当区分:最終著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
Rapid coral species turnover in one of the northernmost coral communities, Uchiura Bay, Shizuoka Prefecture, Japan under a changing climate 査読あり
Morita Mukuto, Fujino Yuichiro, Nagamine Teruki, Fukami Hironobu, Yokochi Hiroyuki, Nomura Keiichi, Asakura Kazuya, Kurihara Haruko, Nakamura Masako, Yasuda Nina
Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 27 ( 1 ) 197 - 204 2025年12月
記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本サンゴ礁学会
Recently, corals have been expanding northwards in response to rising seawater temperatures, highlighting the role of temperate coral communities as potential refugia for subtropical coral species. However, long-term, detailed data on changes in coral species composition at the northernmost distribution limits remain scarce. Here, we investigated the distribution of zooxanthellate scleractinian coral species in one of the northernmost coral habitats, Uchiura Bay, Shizuoka Prefecture, Japan, and compared it with previous documents from 1937 and 1995. We recorded 13 families, 22 genera, and 35 species of corals in Uchiura Bay. Of the 35 species recorded in this study, only nine species were found in both the present survey and the 1995 survey, while 19 species documented in 1995 could not be found in the present study. Furthermore, only five species were commonly found between the 1937, 1995, and 2024 surveys. When comparing with the previous records (reviewed by Kitano et al. 2020), eight coral species including <i>Acropora glauca</i>, <i>Coelastrea incrustans</i>, <i>Leptoseris hawaiiensis</i>, <i>Madracis kirbyi</i>, <i>Montipora</i> cf. <i>floweri</i>, <i>Pavona varians</i>, <i>Pocillopora damicornis</i>, and <i>Porites</i> cf. <i>lobata</i> were newly recorded as one of the northernmost distribution limits. Although some species may have been overlooked due to differences in survey methodologies and efforts, the species composition in this area has likely changed significantly over 87 years. Our results highlight the need to study coral species distributions and their historical shifts by repeated surveys with consistent effort in clearly defined plots. This study emphasizes the need to assess low-density, inconspicuous coral species to better understand distribution dynamics in one of the northernmost habitats under climate change.
-
Hisata Kanako, Nagata Tomofumi, Kanai Megumi, Sinniger Frederic, Nagata Fumihiko, Suwa Mayuki, Yoshioka Yuki, Harii Saki, Nonaka Masanori, Fukami Hironobu, Arakaki Seiji, Fujie Manabu, Arakaki Nana, Zayasu Yuna, Narisoko Haruhi, Noda Takeshi, Koseki Aya, Nishitsuji Koki, Inoue Jun, Shinzato Chuya, Satoh Noriyuki
Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 27 ( 1 ) 13 - 29 2025年5月
記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本サンゴ礁学会
Coral reefs possess the highest biodiversity of all marine ecosystems and zooxanthellate scleractinian corals, the keystone organisms of these reefs, are in crisis due to climate change and anthropogenic activities. Future reef conservation requires comprehensive understanding of the present status of scleractinian taxa in each region. Environmental DNA metabarcoding (eDNA-M) is a method to meet such requirements. Still, it requires optimized primers for PCR amplification of eDNA and complete genomic sequence information for bioinformatic analyses. Coral reefs of Japan reportedly host 85 scleractinian genera. Our previous study developed a primer set that can be used to amplify scleractinian mitochondrial 12S rDNA for eDNA-M analysis. However, at present, the NCBI nucleotide database contains only ~60 genera with available 12S rDNA sequences, indicating that nearly 25 genera that should be detected by this system have no sequence information. To overcome this problem and to establish a nearly complete eDNA-M system for generic level detection of Japanese scleractinians, we collected 22 scleractinian genera and sequenced their mitochondrial genomes. In addition, species of another 12 genera were re-sequenced to avoid sequence differences caused by geographic variation. Incorporation of these data into a newly constructed informatic pipeline resulted in an eDNA-M system that can detect 83 of the 85 genera. This provides a tool for comprehensive, generic level detection of scleractinian corals in Japanese waters.
-
Isomura N., Inoha K., Shimura A., Yasuda N., Kikuchi T., Iwao K., Kitanobo S., Ohki S., Morita M., Fukami H.
Coral Reefs 43 ( 5 ) 1497 - 1509 2024年10月
担当区分:最終著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Coral Reefs
Hybridisation is an evolutionary process that generates genetic diversity in organisms. However, the relationship between reproductive features, such as spawning synchronisation and gamete compatibility, and the degree of introgression leading to hybridisation are poorly understood. The reef-building coral Acropora spp. have a complex evolutionary history, and the link between their ecology, life-history traits, and potential to hybridise is disputed. Here, we examined the relationship among the reproductive features involved in the intercrossing of three species, Acropora florida, Acropora gemmifera, and Acropora intermedia, at two sites: Akajima and the Sesoko islands in southern Japan. Although the examined species showed synchronous spawning and high rates of gamete compatibility, spawning synchronisation and gamete compatibility were less strongly associated with high rates of interbreeding among the three species. Model-based genetic clustering and site-pattern frequency-based tests with single nucleotide polymorphisms supported genetic admixture among the three species in each location. Demographic analyses using fastsimcoal implied that the admixture among the three species in each location might have occurred in the past (> 2,000 generations) and recently (< 50 generations). Furthermore, the recent admixture of these three species is potentially associated with heavy bleaching events and population declines. The principal component analysis, structure, and fastsimcoal showed that the extensive admixture of A. intermedia and A. gemmifera on Sesoko Island occurred recently. Therefore, gamete interactions that lead to hybridisation in the field must be clarified. Furthermore, the connectivity between the two locations needs to be identified; however, our results implied that population fluctuations could be associated with introgression.
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
長崎市高島町の造礁サンゴ図鑑
福留翔太・深見裕伸( 担当: 共著 , 範囲: 全部)
やったろうde高島 2025年11月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
深見 裕伸, 佐々木 圭一, 磯村 尚子, 北野 裕子, 藤井 琢磨( 担当: 共編者(共編著者))
特定非営利活動法人喜界島サンゴ礁科学研究所 2022年7月 ( ISBN:9784991155017 )
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
藤井琢磨,北野裕子,磯村尚子,深見裕伸( 担当: 共編者(共編著者))
喜界島サンゴ礁科学研究所 2020年8月
総ページ数:67 担当ページ:全ページ 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
サンゴの白化ー失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム
深見裕伸 (2章)( 担当: 分担執筆)
成山堂書店 2020年2月
総ページ数:178 担当ページ:32-53 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
Coral Reefs of the World
Naoko Isomura, Hironobu Fukami( 担当: 共著 , 範囲: Coral Reproduction in Japan)
Springer 2018年2月
総ページ数:179 担当ページ:95-110 記述言語:英語 著書種別:学術書
MISC 【 表示 / 非表示 】
-
分類と系統:有藻性イシサンゴ類における分類体系改変の現状2015 招待あり 査読あり
深見裕伸
生物科学 67 ( 4 ) 201 - 215 2016年7月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
-
喜界島の有藻性イシサンゴ類の種組成について 招待あり 査読あり
深見裕伸・北野裕子・立川浩之
月刊海洋 号外 ( 56 ) 94 - 102 2016年5月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
-
Regional specific approach is a next step for setting evolutionary‐based conservation priorities in the scleractinian corals.
H. Fukami
Animal Conservation 4 318 - 319 2015年8月
記述言語:英語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:The Zoological Society of London
-
Fukami H.
Animal Conservation 18 ( 4 ) 318 - 319 2015年8月
-
阿嘉島におけるミドリイシ属サンゴの種分化
磯村尚子, 深見裕伸
みどりいし ( 26 ) 15 - 19 2015年3月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:阿嘉島臨海研究所
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
タカクキクメイシ Favites valenciennesii に対する形態多型の カテゴライズ化と分類学的実態
岸大悟・深見裕伸
日本サンゴ礁学会第27回大会 2024年11月29日
開催年月日: 2024年11月28日 - 2024年12月1日
記述言語:日本語 会議種別:ポスター発表
-
180年間形態多型とされてきたFavites valenciennesii(タカクキクメイシ)に対する形態多型のカテゴライズ化と分類学的実態
岸大悟・深見裕伸
日本動物分類学会 鳥取大会 2024年6月15日
開催年月日: 2024年6月15日 - 2024年6月16日
記述言語:日本語 会議種別:ポスター発表
-
日本で新たに発見されたサザナミサンゴ科の種の紹介
深見裕伸
日本サンゴ礁学会第26回大会 2023年11月24日
開催年月日: 2023年11月23日 - 2023年11月26日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
-
エダミドリイシ (Acropora pruinosa) の形態多様性
福留翔太・深見裕伸
日本サンゴ礁学会第26回大会 2023年11月26日
開催年月日: 2023年11月23日 - 2023年11月26日
会議種別:ポスター発表
-
3 つの形態多型から検討する Favites valenciennesii ( タカクキ クメイシ ) の分類学的実態
岸大悟・深見裕伸
日本サンゴ礁学会第26回大会 2023年11月26日
開催年月日: 2023年11月23日 - 2023年11月26日
会議種別:ポスター発表
受賞 【 表示 / 非表示 】
-
日本サンゴ礁学会 川口奨励賞
2007年11月 日本サンゴ礁学会
深見裕伸
受賞区分:国内学会・会議・シンポジウム等の賞 受賞国:日本国
-
日本サンゴ礁学会ベストプレゼンテーション賞
1999年10月 日本サンゴ礁学会
深見裕伸
受賞区分:国内学会・会議・シンポジウム等の賞 受賞国:日本国
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
過去の気候変動から読み解くミドリイシ属サンゴの適応
研究課題/領域番号:23K23634 2024年04月 - 2026年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
造礁サンゴ類の見えない多様性-その可視化と成因推定および将来予測
研究課題/領域番号:23H00529 2023年04月 - 2026年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(A)
担当区分:研究分担者
-
過去の気候変動から読み解くミドリイシ属サンゴの適応
研究課題/領域番号:22H02369 2022年04月 - 2026年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
日本の温帯域に生息する造礁サンゴの固有性と起源を探る
研究課題/領域番号:18K06423 2018年04月 - 2022年03月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
造礁サンゴ「種分類」の新機軸とその体系化-分子細胞遺伝学的アプローチ-
研究課題/領域番号:17H03861 2017年04月 - 2020年03月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
ベトナム北部のコ・ト海洋保護区におけるサンゴの繁殖時期:サンゴ礁のより良い管理と再生 国際共著
研究課題/領域番号:2020-1 2020年12月 - 2022年12月
公益財団法人長尾自然環境財団 研究者育成支援プログラム(CGF プログラム)
資金種別:競争的資金
-
串間市および周辺海域のサンゴ群集および藻場の生態系調査および保全活用
2013年04月 - 2014年03月
宮崎大学 学長裁量経費(戦略重点経費)
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
宮崎県は、高緯度サンゴ群集が発達している上に、亜熱帯域に近いことから温暖化の影響を直接見ることができる理想的な場所である。特に、県南部の串間市では、2012年に九州最大級のテーブルサンゴの大群落が発見され、観光資源としても注目を浴びている一方で、オニヒトデの食害も問題になっている。また、串間市周辺にはかつてサンゴ群集と並んで豊かな藻場も存在しており良い漁場となっていたが、現在、水温上昇およびそれに伴う植食性魚類の活性化により藻場が減少している状況にある。このように串間市周辺は、藻場の減少とサンゴ群集の増加など藻場とサンゴ群集の関係を調べるのにも最適な場所でもあり、さらに水産および観光面からも注目を浴びている場所でもある。
以上のことから、本研究では、串間市およびその周辺海域のサンゴ群集および藻場の生物相および水質環境などの生態系基盤情報の収集を行うことで温暖化の影響やサンゴと藻場の関係を明らかにするとともに、サンゴ群集の水産資源および観光資源としての価値も探る。 -
宮崎県のサンゴ群集と水産・観光資源の評価・活用
2012年07月 - 2013年03月
宮崎大学農学部 学部長裁量経費
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
宮崎県南部の串間市には大規模なサンゴ群集が2012年に発見された。サンゴ群集は水産資源を含む様々な生物を育む場所および観光資源として世界的に価値が高い。しかし、宮崎県ではそれらサンゴ群集の価値は十分に生かされていない。そこで、右に図示したような研究を行うことで、宮崎県におけるサンゴ群集の水産および観光資源の価値を明らかにする。さらに、串間市でのシンポジウム開催など県民への啓発活動を行い、住民や学生に向けた自然教材としての活用も考慮しながら、広域的なサンゴ群集の活用法を見出す。