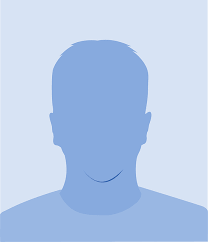|
所属 |
農学部 農学部門海洋生命科学領域 |
|
職名 |
准教授 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
論文 【 表示 / 非表示 】
-
串間市で撮影された水中写真に基づく宮崎県初記録のフエフキダイ科魚類カグツチヨコシマクロダイ
田林 藍・阪本竜也・緒方悠輝也・村瀬敦宣・長友伸二郎
宮崎の自然と環境 ( 10 ) 61 - 62 2025年12月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:宮崎の自然と環境協会
A photographic specimen of a juvenile of Redfin Emperor, Monotaxis heterodon (Lethrinidae), was collected at Meotoura Beach, Kushima City, Miyazaki Prefecture, southern Japan (31º29'29.1"N, 131º23'07.7"E; 9.5–15.1 m depth; 18°C) on 10 January 2013. Previously, the verifiable Japanese record of this species has been known from Okinawa Prefecture. Therefore, the present photo specimen represents the first record from Miyazaki Prefecture.
-
門川湾から得られた標本に基づくハナツノハギの宮崎県からの記録
岩倉 基・栗原 巧・緒方悠輝也・村瀬敦宣
宮崎の自然と環境 ( 10 ) 58 - 60 2025年12月
担当区分:最終著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:宮崎の自然と環境協会
A single specimen (44.0 mm standard length) of the Rhinoceros Leatherjacket, Pseudalutarius nasicornis (TEMMINCK & SCHLEGEL 1850), was collected from Kadogawa Bay (Miyazaki Prefecture, southern Japan). This specimen represents the first reliable record of the species from the prefecture.
-
Ota Y, Sakamoto R, Ogata Y, Kurihara T, Murase A
Acta Ichthyologica et Piscatoria 55 385 - 392 2025年11月
担当区分:最終著者, 責任著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Pensoft Publishers
Zostera japonica Ascherson et Graebner, 1907 is a dominant seagrass species that forms coastal habitats in the northwestern Pacific. Bare areas adjacent to these seagrass beds are also recognized as fish habitat. However, few studies have comparatively evaluated the ecological importance of Z. japonica beds and adjacent bare ground within estuarine environments. We conducted seine net sampling to compare ichthyofaunal composition between Z. japonica beds and adjacent bare ground in a small temperate estuary in Kyushu, southern Japan, during three summer seasons (2015, 2016, and 2019), when seagrass growth is at its peak. Fish species richness and the abundance of the predominant species, Redigobius bikolanus (Herre, 1927), were significantly higher in the seagrass beds than over bare ground. Additionally, the size distribution of R. bikolanus was broader in seagrass beds. PERMANOVA analysis revealed a significant difference in abundance-based species composition between the two habitats, and SIMPER analysis identified three species that contributed most to this distinction: R. bikolanus and Gerres japonicus Bleeker, 1854 (both more abundant in seagrass beds), and Gymnogobius breunigii (Steindachner, 1880) (more abundant over bare ground). These findings imply that Z. japonica beds enhance fish diversity and serve as key habitats for dominant fish species, while adjacent bare ground also supports specific fish communities. The results underscore the importance of conservation efforts within estuaries that account for the ecological roles of both seagrass and bare substrates.
-
Takumi Kurihara, Yukiya Ogata, Murase Atsunobu
Biogeography 28 ( 0 ) 7 - 12 2025年10月
担当区分:最終著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本生物地理学会
分布南限を含む宮崎県からのイシカワシラウオNeosalangichthys ishikawaeの標本に基づく確かな記録.
栗原 巧・緒方悠輝也・村瀬敦宣.
九州東部に位置する宮崎県宮崎市ならびに延岡市沿岸の砕波帯を有する砂浜から計3個体のシラウオ科Salangidae魚類イシカワシラウオNeosalangichthys ishikawae (Wakiya & Takahasi, 1913)の標本(標準体長42.6–51.0 mm)が得られた.本種の分布南限は日向灘海域(大分県から鹿児島県の東九州沿岸)または宮崎海岸(宮崎市宮崎港と一ツ瀬川河口との間に広がる砂浜)とされていたが,これらの記録は,それぞれ具体的な産地が不明の標本と写真個体のみに基づいたものであった.したがって,今回得られた標本は確かな証拠資料に基づく宮崎県における初めてのイシカワシラウオの分布記録となると同時に,宮崎市沿岸から得られた標本は本種の確かな分布南限記録となる.DOI: 10.11358/biogeo.28.7
-
Murase A., Yamasaki Y., Mukai M., Ikehara Y., Ogata Y., Inoue K.
Marine Ecology 46 ( 4 ) 2025年7月
担当区分:筆頭著者, 責任著者 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Marine Ecology
Estuarine lagoons provide nursery habitats for marine fishes; however, small lagoons (< 1 km<sup>2</sup>) have been overlooked. To evaluate the nursery function of small estuarine lagoons (SELs) for temperate marine fish, this study used seining on the coast of the northwestern Pacific (Kyushu, temperate Japan) during the juvenile seasons (winter and spring) to perform juvenile sampling at two scales and an abundance/size comparison of blackfin seabass (Lateolabrax latus). As a preliminary survey, habitat-scale (inside vs. outside lagoon habitats) sampling was attempted in two SELs during February and April. Subsequently, seascape-scale sampling was undertaken during the juvenile season (January–May). The seascape consisted of two types of estuaries (lagoons and rivers) and sandy beaches (embayed and exposed). A preliminary survey showed no clear difference in abundance among the habitats, but significantly larger juveniles were observed inside than outside the two SELs. In the seascape survey, peak juvenile abundance during the first half of the study period was concentrated in habitats other than the lagoon estuary, whereas no peak was recorded during the second half. Moreover, the lagoon estuary was significantly larger than the marine habitats, and the monthly occurrence of juveniles was continuous in the lagoon estuary but intermittent in the riverine estuary. These results imply that seabass juveniles utilize the SEL habitat as they grow, highlighting the potential nursery function of estuarine lagoons for marine fish, even at a small scale.
DOI: 10.1111/maec.70031
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
夏休みの思い出
緒方悠輝也・日高優衣・長友結依・大衛亮正・小原直人・栗原 巧・斎木悠亮・眞田樹也・津守康成・村瀬敦宣( 担当: 共著)
宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド 2022年1月 ( ISBN:978-4-909630-04-9 )
記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
-
Fish Diversity of Japan (Chapter 19)
Atsunobu Murase( 担当: 単著 , 範囲: Chapter 19: Coastal Fishes in Rocky and Coral Reefs)
Springer Nature 2022年1月 ( ISBN:978-981-16-7426-6 )
総ページ数:454 担当ページ:339-346 記述言語:英語 著書種別:学術書
Reef communities are based on hard substrata and habitat-producing organisms such as macroalgae and reef builders, which are affected by various physical factors. Japanese reef fishes are diverse in space and time due to the various aspects of reefs and the different ecological environments around Japan. This chapter summarizes regional and temporal variations in fishes inhabiting rocky and coral-reef habitats (i.e., reef fishes) in the Japanese Archipelago, to reveal how global changes affect fishes. The focus is on the transitional zone, which is sensitive to climate change. Recent studies on reef fishes in Japan showed the effects of the warm Kuroshio Current, reef-building corals and long-term sea warming on the establishment of tropical reef fishes in temperate Japan. Furthermore, recent reports on the distribution limits of several cool-temperate fishes indicate the importance of ocean currents and the geomorphology of the coast as limiting factors in the distribution of cool-temperate fishes, while the interactions among fishes of different biogeographic affinities are unclear. In the future, sustainable assessment methods (in terms of cost and effort) are expected to be adopted in ecological studies on reef fishes, to understand and monitor the dynamics of and interactions among reef fishes in Japan.
-
Fish Diversity of Japan (Chapter 24)
Yusuke Miyazaki and Atsunobu Murase( 担当: 共著 , 範囲: Chapter 24: Using Gyotaku to Reveal Past Records of Fishes Including Extinct Populations)
Springer Nature 2022年1月 ( ISBN:978-981-16-7426-6 )
総ページ数:454 担当ページ:409-418 記述言語:英語 著書種別:学術書
Japan has developed unique customs related to recreational fishing. Gyotaku, which means “fish impression” or “fish rubbing” in English, has become common since the last Edo Period. A gyotaku is made by copying an image of a fresh fish specimen to paper using ink. Information such as capture locality and sampling date were often written on a gyotaku sheet, and these can be useful with respect to past biodiversity data. Some fish targets of gyotaku (i.e., popular targets of recreational fishing) have been listed as threatened species in the Japanese red lists because their habitats have been seriously degraded. Some gyotaku targets are able to be identified to species using gyotaku alone, particularly if external morphologies such as number of scales or scale rows are distinguishing characters. Two examples of the families Sparidae and Sillaginidae are discussed, and the latter includes new distributional records for Sillago parvisquamis. This species has been listed as critically endangered, and only one gyotaku sheet of the species caught from the Tokyo Bay was previously known. Additional sheets from Tokyo Bay are reported here, with identifications based on the gyotaku alone. As shown herein, data mining from historical materials such as gyotaku can help clarify past biodiversity.
-
新・門川の魚図鑑:ひむかの海の魚たち
村瀬敦宣・緒方悠輝也・山﨑裕太・三木涼平・和田正昭・瀬能 宏( 担当: 編集 , 範囲: 編集・執筆)
宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド 2021年3月 ( ISBN:978-4-909630-03-2 )
総ページ数:358 記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
-
門川おさかなガイドブック:さかなのまちの漁業と水辺
緒方悠輝也, 山﨑裕太(編著), 村瀬敦宣(監修)( 担当: 監修)
宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド 2021年1月
総ページ数:40 記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
MISC 【 表示 / 非表示 】
-
魚類の多様性に基づく宮崎県沿岸の生態学的評価 招待あり
村瀬敦宣
水環境学会誌 43 ( 7 ) 232 - 235 2020年7月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:日本水環境学会
その他リンク: https://www.jswe.or.jp/publications/journals/index.html
-
村瀬敦宣
宮崎の自然と環境 ( 4 ) 52 - 58 2019年12月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他) 出版者・発行元:宮崎の自然と環境協会
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
エスチャリー魚類の生物地理組成に基づく日本列島の海洋気候帯区分
緒方悠輝也・村瀬敦宣
日本生物地理学会第77回大会(オンライン開催) (ウェブ大会) 日本生物地理学会
開催年月日: 2023年4月9日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:ウェブ大会
西村(1992)は,海洋動物群集の分布パターンに基づいて日本列島周辺の海域を7つの海洋気候帯区として区分した.この分類は,日本列島の地形や海流の特徴を反映しており,これまでの海洋生物地理学的研究の基盤情報とされてきた.一方で,この気候帯区分の根拠となる動物群集の種名や,分布に関するデータは示されておらず,その妥当性についてこれまでに検証されていなかった.また,近年の各地域における魚類相の研究成果により,上記の気候帯区分には改訂の必要性が出てきたことも否めない.本研究では,近年報告された沿岸性魚類相調査の結果および冬季水温の分布データを基に,西村の海洋気候帯区分について再検討するとともに,この区分の妥当性を,日本列島のエスチャリー(淡水と海水が混合する半閉鎖的環境)魚類群集の分布データを基に検証した.海洋気候帯区分の再検討の結果,明瞭に区別される4つの海洋気候帯区(北日本;本土内湾域;本土黒潮流域;南西諸島)が見出された.この気候帯区分の妥当性の検証のため,日本列島のエスチャリーに出現する魚類の文献情報を集約し、各魚種を3通りの生物地理組成(冷温帯種・暖温帯種・熱帯種)に分類し,各気候帯区分内にある複数地点でそれぞれの組成の種数と多様性の割合を算出し,気候帯区分間でこれらの数値の比較を行った.その結果,冷温帯種は北日本,暖温帯種は本土内湾域および本土黒潮流域、熱帯種は南西諸島で有意に種数が高くなった.特筆すべきこととして,ほぼ同じ緯度間でも気候帯区が異なると熱帯種の割合が有意に異なることが明らかになった.以上の結果より,今回定義した新たな海洋気候帯区分の妥当性が示されたと言える.一方で,北部は既往のデータが不足していたために,今回分類した北日本の中に複数の気候帯区が含まれている可能性が残されている.従って,今後は日本海や北海道の沿岸における魚類相データの充実が必要である.
その他リンク: https://biogeography.iinaa.net/image/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%9D%91%E7%80%AC.pdf
-
栗原 巧・緒方悠輝也・中西健二・井上海斗・村瀬敦宣
日本生物地理学会第77回大会(オンライン開催) (ウェブ大会) 日本生物地理学会
開催年月日: 2023年4月9日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:ウェブ大会
河口域・砂浜海岸・潟湖などの沿岸環境は,水産上重要種を含む生物群集にとって,摂餌や捕食者からの回避などの機能を有する成育場を提供し,人類にとっても,文化的・経済的価値の高い最も重要な場所の一つとされる一方で,人為的な攪乱の影響にさらされやすくもある.近年では,これら複数の生息環境の連続性が沿岸生物群集の生産に重要であることがわかってきており,各環境の成育場機能を明らかにするためには,単一の生息環境のみならず,海岸景観の視野に基づいた比較研究の必要性が強調されている.宮崎県延岡市南部の沿岸は南北約4kmの沿岸に複数の生息環境(河口域・開放的砂浜・閉鎖的砂浜・潟湖)を有している.本研究では,この複数の環境で地曳網による魚類仔稚魚の定量調査を1年間経月で行い,採集された河口域魚類(河口域周辺で産卵:マハゼ・ヒメハゼ・ビリンゴ)と海産魚類(海域で産卵:クロサギ・ボラ・ヒイラギ・シロギス)の密度および体長分布を時空間的に比較することで,各環境の有する成育場機能を評価することを目的とした.結果として,河口域魚類と海産魚類で異なる成育場の選択が見受けられ,さらに河口域および海産魚類それぞれの種間でも顕著な違いが見出された.また,過去の研究において,砕波帯を有する砂浜海岸は多様な魚類の成育場として機能するとされていたが,本研究では一部の海産魚類をのぞき,波の影響の強い開放的砂浜は各魚種にとって成育場としての生産性が他の環境よりも低くなる結果が得られた.以上の結果から,複数の沿岸環境の存在が,複数の生活史型の多様な魚種の成育場を提供しており,波の荒い環境は,多くの魚類にとっては環境間をつなぐ通り道として機能していることが示唆された.
その他リンク: https://biogeography.iinaa.net/image/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%A0%97%E5%8E%9F%E3%81%BB%E3%81%8B.pdf
-
小原直人・齊木悠亮・緒方悠輝也・村瀬敦宣
日本生物地理学会第77回大会(オンライン開催) (ウェブ大会) 日本生物地理学会
開催年月日: 2023年4月9日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:ウェブ大会
外来種とは,国内外問わず人為的に導入された生物のことを指し,外来種による在来種に対する捕食・競争による影響が問題視されている.純淡水魚は,海を介した移動ができないことや地域固有性が高く遺伝的特徴が異なる事などの理由により,外来種や外来個体群による影響を受けやすい.特に宮崎県は純淡水魚の固有種の多様性が低く,外来魚の侵入を受けやすいと想定される.本研究では,宮崎県における外来魚対策の基盤情報の構築のため,これまでに報告されている県内の淡水域における外来魚類の記録を再検討するとともに,県内全域の15水系において調査した外来種の出現記録に関して報告する。 宮崎県内の淡水域における外来魚の野外調査は,2015~2022年までの期間に実施し,魚類の採集には,主に手網・投網・さで網・釣りを用いた.得られた標本・画像資料は,証拠資料として一部を除き公的な博物館に登録・保管した. 本研究では,国外・国内それぞれ11種と12種,合計23種の外来種が記録された.外来種の侵入可能な場所は一般的に以下のような特徴をもつ:1)原産地と環境が類似してる;2)人為的な攪乱が多い;3)在来種が少ない.宮崎県は,アユやヤマメなどの放流が行われてきた過去があり,これらの種の放流による上記2)の人為的な攪乱の可能性がある.さらに,宮崎県の淡水魚類相は貧弱であるとされているため,上記3)の特徴もよくあてはまる.以上のことから,宮崎県は,上記1)の条件,すなわち各外来種にとって適した環境があれば,侵入・定着が容易であると考えられる.今回記録された種のうち,既に定着が確認されている種および上記1)の条件を満たしていると考えられる種は, 9割以上(21種)であった.そのため,今後は行政等と連携してこれらの外来魚類の継続した生息状況の把握に努めると共に,在来種への影響に関しても調査・検討していく必要があるだろう.
その他リンク: https://biogeography.iinaa.net/image/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B0%8F%E5%8E%9F%E3%81%BB%E3%81%8B.pdf
-
ヒラスズキ稚魚は成育場として閉鎖的なエスチャリー環境を選択する
山﨑裕太・向井実佳・池原悠太・緒方悠輝也 ・河野秀伸・中西健二・井上海斗・村瀬敦宣
2020年度日本魚類学会年会(ウェブ大会) (ウェブ大会) 日本魚類学会
開催年月日: 2020年10月31日 - 2020年11月1日
記述言語:日本語 会議種別:ポスター発表
開催地:ウェブ大会
-
宮崎県門川町の魚類を題材としたかるた制作による環境教育活動の試み
津守康成,緒方悠輝也,村瀬敦宣,山﨑裕太,秦友一朗,野中大成,齋藤 碧,小林優也,阪本竜也,加藤汰郎,三木涼平,堀井日向,渋谷風雅,眞田樹也
第31回魚類生態研究会 (九州大学病院キャンパス) 九州大学農学部水産増殖学研究室
開催年月日: 2020年2月8日 - 2020年2月9日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:九州大学病院キャンパス
Works(作品等) 【 表示 / 非表示 】
-
2023年6月27日
作品分類:教材 発表場所:門川町立草川小学校、門川町立門川小学校、門川町立五十鈴小学校
この下敷きは門川町の山と川の豊かさを子どもたちをはじめとする一般の方々に手軽に知ってもらうことを目的に制作された。この作品はリバーシブルのデザインになっていて、表側には門川町内を流れる五十鈴川の淡水域でみられる魚12種類の写真と簡単な解説を掲載しており、概ねこの水域でみられる淡水魚を誰にでも把握できるようになっている。裏返すと、門川町内の河川河口域でみられる代表的な魚16種の写真と解説が掲載されており、海水が混じるような環境でみつけることのできる魚がひと目でわかるようになっている。また、背景のイラストは元宮崎大学農学部海洋生物環境学科の学生が描いたもので、表は門川町の西部にある西門川地域の山林と五十鈴川、里山の雰囲気を表現したデザインになっている。裏の背景は五十鈴川河口付近の雰囲気を表現しており、川の出口の先には、町の無人島である乙島が描かれている。
-
さかなのまち 門川の魚かるた
緒方悠輝也,山﨑裕太,津守康成,村瀬敦宣,秦友一朗,野中大成,齋藤 碧,小林優也,阪本竜也,加藤汰郎,三木涼平,堀井日向,渋谷風雅,眞田樹也
2020年10月30日 - 現在
作品分類:教材
『宮崎県のさかなのまち 門川の魚図鑑』に掲載された魚種のうち、門川湾周辺海域で代表される44種をかるたにした『門川の魚かるた』の販売版で、パッケージデザインのほか、解説書や数点の絵札・読み札を改訂したリニューアル版。門川町内で販売されているほか、門川町のふるさと納税のお礼の品にも選定されている。
-
門川の魚かるた
緒方悠輝也,津守康成,村瀬敦宣,山﨑裕太,秦友一朗,野中大成,齋藤 碧,小林優也,阪本竜也,加藤汰郎,三木涼平,堀井日向,渋谷風雅,眞田樹也
2020年1月31日 - 現在
作品分類:教材
受賞 【 表示 / 非表示 】
-
平成29年度 高等教育コンソーシアム宮崎「公募型卒業研究テーマ成果発表会」口頭発表最優秀賞
2018年3月 高等教育コンソーシアム宮崎 宮崎県延岡市における河口域魚類の多様性ー魚類相から見た地域の価値
緒方悠輝也(村瀬敦宣共同発表)
受賞国:日本国
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
流域環境管理と防疫調査を繋ぐ河川-河畔生物一斉調査手法の開発
研究課題/領域番号:25K00041 2025年04月 - 2029年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
温暖化と関連した沿岸生物多様性モニタリングサイトの選定―黒潮流域に注目して
研究課題/領域番号:15H06514 2015年10月 - 2017年03月
科学研究費補助金 若手研究(スタートアップ)
担当区分:研究代表者
本研究は,黒潮流域では水温上昇による南方種の移動が起こりやすいこと,および黒潮流域の水温分布の階層構造に注目し,沖縄から房総半島にいたる黒潮流域の複数地点の潮間帯性の魚類・貝類群集の構造を明らかにし,この流域の中でも大隅諸島から東九州の沿岸域が温暖化に関連した沿岸生物相の長期モニタリングを行うのに適した地域であることを示す.
受託研究受入実績 【 表示 / 非表示 】
-
門川町の生物多様性に関する調査並びに魅力の情報発信に関する研究
2021年07月 - 2026年03月
門川町 一般受託研究
片岡 寛章、村瀬 敦宣
担当区分:研究分担者 受託研究区分:一般受託研究
-
門川町の生物多様性に関する調査並びに魅力の情報発信に関する研究
2021年07月 - 2022年03月
門川町
担当区分:研究分担者 受託研究区分:一般受託研究
-
稚仔魚期のアユの生態および資源状況に関する研究
2020年11月 - 2021年03月
宮崎県 一般受託研究
担当区分:研究代表者 受託研究区分:一般受託研究
-
門川町の生物多様性に関する調査並びに魅力の情報発信に関する研究
2020年04月 - 2021年03月
門川町 一般受託研究
担当区分:研究分担者 受託研究区分:一般受託研究
研究・技術シーズ 【 表示 / 非表示 】
-
宮崎県沿岸の魚類相の把握

魚類を対象とした日本列島沿岸の海洋生物地理学的研究
エスチャリー(河口域)とその周辺環境の魚類による利用様式の解明ホームページ: 宮崎大学延岡フィールド
技術相談に応じられる関連分野:・沿岸性魚類の同定
・魚種から見た河口・沿岸域の環境評価
・水生生物ガイド・図鑑制作メッセージ:当研究室は野外調査が好きな人が集まります。また、水生生物をテーマにした環境教育を行ったり、魚かるたなどの教材も作ったりしています。水辺の生きものが好きで、その楽しさを知ってもらいたい、と思っている人にとっても楽しめる研究室だと思います♪