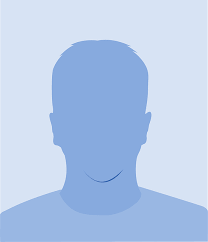|
所属 |
教育学部 理科教育 |
|
職名 |
講師 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
学位 【 表示 / 非表示 】
-
博士(理学) ( 2021年3月 名古屋大学 )
-
修士(理学) ( 2018年3月 名古屋大学 )
-
学士(理学) ( 2016年3月 九州大学 )
研究キーワード 【 表示 / 非表示 】
-
炭酸塩コンクリーション
-
湖成層
-
温室期の地球環境
-
化石化プロセス
-
チャート
-
シリカコンクリーション
-
化石
-
コンクリーション
-
堆積学
-
古気候学
-
古環境学
学歴 【 表示 / 非表示 】
-
名古屋大学 大学院環境学研究科
- 2021年3月
-
名古屋大学 大学院環境学研究科
- 2018年3月
-
九州大学 理学部 地球惑星科学科
- 2016年3月
学外略歴 【 表示 / 非表示 】
-
日本大学 文理学部 助手
2023年4月 - 2024年3月
-
早稲田大学 教育・総合科学学術院 非常勤講師
2022年4月 - 2022年9月
-
名古屋大学 宇宙地球環境研究所 研究員
2021年4月 - 2023年3月
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Ammonite concretion formation through organic decomposition in the iron reduction zone 査読あり
Yusuke Muramiya, Hidekazu Yoshida, Nagayoshi Katsuta, Ryusei Kuma, Tomoyuki Mikami
Journal of Sedimentary Research 2023年11月
掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Society for Sedimentary Geology
The ammonites in spherical carbonate concretions often preserve their original three-dimensional (3D) shell shapes and detailed fragile structures. However, the formation process of spherical ammonite concretion is not fully understood. Herein, the ammonite concretions identified in the Cretaceous (Campanian) Osoushinai Formation, Yezo Group, Japan, are examined to understand their formation process during the soft tissue decomposition after burial in marine sediments. In the Osoushinai Formation, almost all observed ammonites in concretions preserve their 3D form without phragmocone deformation. The calcite filling in the remaining body chamber of ammonites (BC1) shows that shells were buried with soft tissues. These occurrences, negative delta13C values, and the near-zero delta18O values of BC1 as well as the concretions indicate that both BC1 and concretions rapidly formed from dissolved inorganic carbon derived from organic matter, including the soft tissue of dead organisms, in the shallow part of the sediments. The increasing Fe concentration in BC1 shows that BC1 formed in the iron reduction (FeR) zone, where organic matter was decomposed owing to the activity of iron-reducing microorganisms. The similarity of the elemental and isotopic compositions of BC1 and concretions show that they concurrently formed in the FeR zone. In the Osoushinai Formation, an abundant influx of Fe(III) and intense bioturbation during the deposition of the formation promoted organic decomposition in the FeR zone, causing rapid formation of BC1 and concretions. Such rapidly formed calcite fillings and concretions protected fossils from deformation and dissolution during diagenesis to preserve their 3D form. Overall, the findings of this study provide a new insight into the relation between sedimentary environments and the fossil preservation process via rapid concretion formation.
DOI: 10.2110/jsr.2023.078
-
愛知県南知多町先苅貝塚における貝形虫化石 査読あり
佐々木聡史, 隈隆成
名古屋大学年代測定研究 7 32 - 35 2023年3月
掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
双葉層群足沢層(上部白亜系コニアシアン階下部)浅海成細粒砂岩の大型アンモナイト密集層と巨大炭酸塩コンクリーション濃集層 査読あり
大森 光, 安藤 寿男, 村宮 悠介, 歌川 史哲, 隈 隆成, 吉田 英一
地質学雑誌 129 ( 1 ) 105 - 124 2023年2月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本地質学会
いわき市アンモナイトセンターの双葉層群足沢層大久川部層(コニアシアン下部)のアンモナイト(主に径40-60 cmの<i>Mesopuzosia yubarensis</i>)密集層と直下にある炭酸塩コンクリーション濃集層の,堆積相・産状観察と地球化学分析から形成過程を考察した.<i>M. yubarensis</i>は,沖合いの生息場から死後浮遊で沿岸に達した軟体部の失われた殻が,ストーム波浪で住房部が破壊され,分級・集積・運搬され,下部外浜沖合い側で癒着HCS極細粒砂層のハンモックマウンドに沿って急速に埋積した.炭酸塩コンクリーションは,多様なサイズ(径15-194 cm)の長-扁球形で,密集しながらも比較的一様に分布する.コンクリーションの形成は,ストーム波浪で運搬された有機物と底質中のベントス遺骸の分解に伴って堆積物の浅所で始まり,その後,埋没に伴い堆積物深所におけるメタン生成帯での有機物分解が生じるまで継続した.
-
男鹿半島鵜ノ崎海岸の中新統西黒沢層・女川層中に見られる巨大鯨骨ドロマイトコンクリーション群の形成条件 査読あり
隈 隆成, 西本 昌司, 村宮 悠介, 吉田 英一
地質学雑誌 129 ( 1 ) 145 - 151 2023年2月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本地質学会
Carbonate concretions occur in sedimentary rocks of widely varying geological ages throughout the world. Recently, more than 100 gigantic carbonate concretions with diameters ranging from 1 to 9 m have been identified along the Unosaki coast of Oga Peninsula, Akita Prefecture, Japan. The formation process of such gigantic concretions, some of which along the Unosaki coast contain whale bones, remains uncertain. A mineral composition analysis reveals that the major mineral of the concretions is dolomite. Considering the location of dolomite precipitation, their composition implies that the concretions were formed in a reducing environment in which sulfate ions were removed. Stable carbon and oxygen isotopic analysis reveals that the CaCO<sub>3</sub> of whale bone and concretions contains light δ<sup>13</sup>C and heavy δ<sup>18</sup>O, suggesting that whale organic matter contributed to the formation of the concretions. The gigantic carbonate concretions were presumably formed by the accumulation and burial of whale carcasses with high sedimentation rates, and subsequent reaction of carbon decomposed by benthic and microbial activity with seawater.
-
Hitoshi Hasegawa, Nagayoshi Katsuta, Yasushi Muraki, Ulrich Heimhofer, Niiden Ichinnorov, Hirofumi Asahi, Hisao Ando, Koshi Yamamoto, Masafumi Murayama, Tohru Ohta, Masanobu Yamamoto, Masayuki Ikeda, Kohki Ishikawa, Ryusei Kuma, Takashi Hasegawa, Noriko Hasebe, Shoji Nishimoto, Koichi Yamaguchi, Fumio Abe, Ryuji Tada, Takeshi Nakagawa
Scientific Reports 12 ( 1 ) 2022年12月
掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Springer Science and Business Media LLC
Abstract
Understanding climate variability and stability under extremely warm ‘greenhouse’ conditions in the past is essential for future climate predictions. However, information on millennial-scale (and shorter) climate variability during such periods is scarce, owing to a lack of suitable high-resolution, deep-time archives. Here we present a continuous record of decadal- to orbital-scale continental climate variability from annually laminated lacustrine deposits formed during the late Early Cretaceous (123–120 Ma: late Barremian–early Aptian) in southeastern Mongolia. Inter-annual changes in lake algal productivity for a 1091-year interval reveal a pronounced solar influence on decadal- to centennial-scale climatic variations (including the ~ 11-year Schwabe cycle). Decadally-resolved Ca/Ti ratios (proxy for evaporation/precipitation changes) for a ~ 355-kyr long interval further indicate millennial-scale (~ 1000–2000-yr) extreme drought events in inner-continental areas of mid-latitude palaeo-Asia during the Cretaceous. Millennial-scale oscillations in Ca/Ti ratio show distinct amplitude modulation (AM) induced by the precession, obliquity and short eccentricity cycles. Similar millennial-scale AM by Milankovitch cycle band was also previously observed in the abrupt climatic oscillations (known as Dansgaard–Oeschger events) in the ‘intermediate glacial’ state of the late Pleistocene, and in their potential analogues in the Jurassic ‘greenhouse’. Our findings indicate that external solar activity forcing was effective on decadal–centennial timescales, whilst the millennial-scale variations were likely amplified by internal process such as changes in deep-water formation strength, even during the Cretaceous ‘greenhouse’ period.
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
始新世“温室期”の陸域環境変動の復元に向けたグリーンリバー湖成層の古地磁気層序の構築
松本裕貴,穴井千里,長谷川精,泉奏,池原実,佐久間杏樹,隈隆成
高知大学海洋コア国際研究所令和6年度共同利用・共同研究成果発表会 2025年3月
開催年月日: 2025年3月
会議種別:口頭発表(一般)
-
始新世“温室期”の陸域気候復元に向けたグリーンリバー湖成層の古地磁気層序の構築
松本裕貴,穴井千里,長谷川精,佐久間杏樹,泉奏,隈隆成
日本地質学会中国支部会 2024年12月
開催年月日: 2024年12月
会議種別:口頭発表(一般)
-
メゾンクリークの菱鉄鉱質コンクリーション群におけるコンクリーション中の炭素量と化石サイズの関係
村宮悠介, 三上智之, 吉田英一, 勝田長貴, 隈 隆成
日本古生物学会第172回例会 2023年2月
開催年月日: 2023年2月
会議種別:ポスター発表
-
初期続成過程における鉄還元帯でのアンモナイトコンクリーションの形成
村宮悠介, 吉田英一, 勝田長貴, 隈隆成, 三上智之
日本地質学会学術大会(Web) 2023年
開催年月日: 2023年
会議種別:口頭発表(一般)
-
完新世炭酸塩コンクリーションの<sup>14</sup>C分析から探る形成プロセス
南雅代, 隈隆成, 吉田英一
日本地球化学会年会要旨集(Web) 2023年
開催年月日: 2023年
会議種別:ポスター発表
受賞 【 表示 / 非表示 】
-
最優秀発表賞
2021年3月 令和2年度高知大学海洋コア総合研究センター共同利用・共同研究成果発表会 米国グリーンリバー湖成層に記録された始新世前期~中期“温室期”の古環境変動
隈隆成, 長谷川精, 大島有希子, 石川航輝
受賞区分:国内外の国際的学術賞
-
学生優秀発表賞
2019年5月 日本地球惑星科学連合大会2019年 米国グリーンリバー層に見られる湖成チャートの堆積リズムと湖生物生産との関係性
隈隆成, 長谷川精, 山本鋼志, 吉田英一, 池田昌之, 勝田長貴, Whiteside J.
受賞区分:国内学会・会議・シンポジウム等の賞
-
最優秀講演賞(SSJ Best Talk Award)
2018年 日本堆積学会秋田大会 「北米グリーンリバー湖成層に見られるチャート層の成因と始新世前期“温室期”の湖生物生産量変動」
隈隆成, 長谷川精, 山本鋼志
受賞区分:国内学会・会議・シンポジウム等の賞
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
米国ユタ州の年縞湖成層から読み解く気候転換点を超えた始新世“温室期”の気候安定性
研究課題/領域番号:23KK0193 2023年09月 - 2026年03月
日本学術振興会 科学研究費基金 国際共同研究加速基金(海外連携研究)
長谷川 精, 佐久間 杏樹, 隈 隆成
担当区分:研究分担者
-
生物起源炭酸塩コンクリーションの初期続成メカニズムの解明
研究課題/領域番号:21K20381 2021年08月 - 2023年03月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援 研究活動スタート支援
隈 隆成
担当区分:研究代表者
これまでに名古屋港海底未固結堆積泥中から産出したウニ,カニ,貝などを核として形成された炭酸塩コンクリーションを対象に,顕微鏡観察,X線を用いた元素マッピングを行った.また,コンクリーション外殻部・内殻部・化石本体部に分けて,安定炭素同位体比分析,元素組成分析,鉱物組成分析,放射性炭素年代測定を行い,炭酸塩コンクリーションの成因とコンクリーションの形成年代を検討した.産状として,名古屋港のコンクリーションはサイズが数mm~数cmであった.また,コンクリーションは沖積層から産出しており,未固結な堆積物中で形成されたと考えられる.特にカニ類は,骨格が維持されていることから,死後,急速にコンクリーション化したことが示唆された.
顕微鏡観察及び元素マッピングの結果,すべてのコンクリーション部に,1 mm程度のペレットが観察された.主要鉱物組成はドロマイトであり,ドロマイトが沈殿するような嫌気的な堆積環境下でコンクリーションが形成されたことが示唆された.安定炭素同位体比は,化石本体部よりコンクリーション部の方が重い値を示し,放射性炭素年代はおおよそ8000年前という結果が得られたが,総じて化石本体部よりコンクリーション部の方が数百年ほど古い値を示した.これは,コンクリーション部には,ペレットともに土壌有機物に由来する古い炭素が含まれているからだと考えられる.約8000年前は縄文海進の時期に相当し,浅海域に生息していた生物が環境変化によって死滅し,化石化したと考えられる. -
年縞湖成層から探る白亜紀中期および始新世前期“超温室期”の年スケール気候変動
研究課題/領域番号:16K21095 2016年04月 - 2018年03月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 若手研究(B)
長谷川 精, 隈 隆成
担当区分:研究代表者
本研究は,モンゴル・シネフダグ層と米国・グリーンリバー層を対象とし,白亜紀中期および始新世前期“温室期”における年~万年スケール気候変動の実態解明を試みてきた.
シネフダグ層に対して蛍光顕微鏡を用いた夏季藻類生産量変動の復元と,μXRFコアスキャナーを用いた降水量指標変動の復元を行った結果,約11年,90~125年,210~240年,400~500年,1000~1450年,2000~2300年といった太陽活動変動と類似した周期性で変動していた.
またグリーンリバー層の堆積相解析と採取試料の主要・微量元素組成の分析を行った結果,湖生物生産量が始新世前期の日射量変動を反映して変動していた.
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
男鹿半島鵜ノ崎海岸のシリカコンクリーションの成因解明
2023年
秋田県ジオパーク連絡協議会 令和5年度秋田県ジオパーク研究助成事業
担当区分:研究代表者
-
男鹿半島鵜ノ崎海岸に見られるコンクリーション化したハンモック状斜交層理砂岩の形成プロセス
2022年
秋田県ジオパーク連絡協議会 令和4年度秋田県ジオパーク研究助成事業
担当区分:研究代表者
-
‘巨大鯨骨コンクリーション群’の成因究明
2021年
秋田県ジオパーク連絡協議会 令和3年度秋田県ジオパーク研究助成事業
担当区分:研究代表者
-
米国グリーンリバー湖成層から探る始新世温室期の数年~数十万年スケールの陸域気候変動
2019年
公益財団法人深田地質研究所 深田研究助成 2019年度
担当区分:研究代表者
社会貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
令和6年度 第11回 宮崎県高等学校課題研究発表大会 審査委員
宮崎県教育委員会 2025年3月13日
-
みやだいwakuwaku体験「何が出るかな?化石発掘体験!」
役割:講師, 助言・指導, 企画, 実演
宮崎大学 大学開放事業 2024年11月16日
-
宮崎県サイエンスコンクール・プレゼンテーション審査委員長(小学生の部)
翔け!未来の科学者育成推進委員会 2024年11月9日
-
宮崎県サイエンスコンクール中央審査 審査委員長(小学生の部)
翔け!未来の科学者育成推進委員会 2024年10月8日
-
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校「総合的な学習の時間」における出前授業
役割:講師
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 2024年7月10日