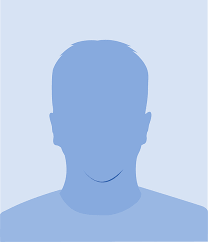|
所属 |
教育学部 社会科教育 |
|
職名 |
教授 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
学位 【 表示 / 非表示 】
-
博士(文学) ( 2008年9月 北海道大学 )
-
修士(文学) ( 1995年3月 北海道大学 )
-
文学士 ( 1993年3月 北海道大学 )
-
政治学士 ( 1988年3月 早稲田大学 )
論文 【 表示 / 非表示 】
-
"“Choosing for Disability” and Parental Virtue" 査読あり
柏葉武秀
Journal of Philosophy and Ethics in Health Care and Medicine 17 3 - 24 2023年12月
記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
中学校道徳科における「哲学対話」の実践と 生徒の哲学的思考の検討
椋木香子, 柏葉武秀, 有吉美春
宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター研究紀要 ( 29 ) 17 - 30 2021年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
中学「特別の教科 道徳」教科書を倫理学的に分析する ―「臓器移植」を題材とする授業をめぐって―
柏葉武秀
宮崎大学教育学部紀要 ( 95 ) 55 - 63 2020年8月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
障害者権利擁護の観点からの出生前診断批判はなにを含意するのか
柏葉武秀
宮崎大学教育学部紀要 ( 89 ) 13 - 24 2017年8月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
Cam Philip, 衛藤 吉則, 柏葉 武秀, 菊地 建至, 中川 雅道, 森 秀樹, 桝形 公也( 担当: 共訳)
萌書房 2017年5月
担当ページ:75-100 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
『近代哲学の名著』
熊野純彦( 担当: 共著 , 範囲: 「スピノザ『エチカ』」204−213頁)
中央公論新社 2011年5月
記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
-
『現代倫理学』
坂井昭宏、柏葉武秀( 担当: 共著 , 範囲: 第3章 正義と善への問い、あとがき)
ナカニシヤ出版 2007年5月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
『哲学の問題群』
麻生博之、城戸淳( 担当: 共著 , 範囲: VI 善悪と価値)
ナカニシヤ出版 2006年5月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
キテイの障害児出生防止論批判を検討する
柏葉武秀
第42回日本医学哲学・倫理学会大会 2023年10月15日
開催年月日: 2023年10月15日
会議種別:口頭発表(一般)
-
「倫理学者」は「初等・中等教育の道徳科授業にどのように貢献できるか」
柏葉武秀
日本倫理学会ワークショップ 「初等・中等教育に対する倫理学の貢献可能性―道徳的諸価値への倫理学的アプローチ」
-
中学「特別の教科 道徳」教科書を倫理学的に分析する—「臓器移植」を題材とする授業をめぐって—
柏葉武秀
日本倫理道徳教育学会第4回大会 (東京大学) 日本倫理道徳教育学会
開催年月日: 2019年12月22日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:東京大学
-
スピノザ実体一元論再考
柏葉武秀
西日本哲学会 第64回大会 (九州産業大学) 西日本哲学会
開催年月日: 2013年11月30日
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:九州産業大学
-
「正義論と障害者の生−配分的正義の射程をめぐって−」
柏葉武秀
西日本哲学会第61回大会 (鹿児島大学) 西日本哲学会
開催年月日: 2010年12月4日 - 2010年12月5日
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:鹿児島大学
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
生殖倫理における徳倫理学的アプローチの研究
研究課題/領域番号:18K00043 2018年04月 - 2025年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
生殖補助医療と遺伝子テクノロジーの進展は、生殖に関する倫理の問題圏に深刻な課題を 生じさせている。生まれてくる子どもの性別、障害の有無だけではなく、いまや特定の能力 増強(エンハンスメント)までもが、親の前に現実的な選択肢として用意されているのであ る。本研究では選択という行為そのものを、「善い親」がなす行為といえるかとの観点から 探求するものである。つまり、親の行為の道徳的正当性を、それが「親の徳」にかなうとい えるかとの観点のもとで究明する。
具体的には、受精から妊娠、出産へと至る人間の生殖に関わる倫理的問題を徳倫理学の見 地から考察する。とりわけHursthouseの新アリストテレス主義徳倫理学の理論的射程を検討 する。その理由は、彼女らの議論こそが「善い親」が備えてしかるべき徳あるいは態度を明 らかにする倫理学的枠組みをほぼ唯一与えているからである。 -
障害学への応答を目的とした徳倫理学の再検討
研究課題/領域番号:25370023 2013年04月 - 2017年03月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
これまで倫理学の議論においては、障害者は「限界事例」の典型として扱われてきた。出生前診断の道徳的正当化をめぐる論争がその例となろう。このような障害あるいは障害者像は、障害者独自の主体性を確立し、あるいは障害を固有の文化として擁護していく障害学によって厳しく批判されている。応募者はこの間、障害学のインパクトを正面から受け止めながら、障害学と倫理学との理論的連携可能性を考察してきた本研究はその研究を発展的に継続するものである。そのさい、倫理学理論のなかでも、とくに徳倫理学を基軸とした倫理学的思考と障害学の根本主張との対質させつつ、相互の理論的深化を図ることを研究目的に設定している。
-
障害学と倫理学との理論的連携の探求
研究課題/領域番号:22520027 2010年03月 - 2013年03月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
1970年代以降イギリスとアメリカで障害学という学問が勃興した。障害学とは、障害と障害者を医療や社会福祉の観点からではなく、積極的な社会参加を可能とする障害者独自の主体性を確立し、あるいは障害を固有の文化として擁護していく学問あるいは思想運動である。日本でも2003年に「障害学会」が創設され、多彩な研究者による学術的な蓄積がなされつつある。本研究はこの障害学と倫理学との理論的連携可能性を考察することを目的としている。