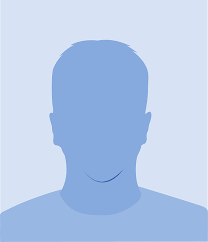|
Affiliation |
Faculty of Medicine School of Nursing Parenting generation and child health nursing course |
|
Title |
Lecturer |
|
Related SDGs |
Papers 【 display / non-display 】
-
特集 周産期感染症2026 産科からみた周産期感染症 50.妊婦および挙児希望女性が海外渡航する場合の感染への留意点 Reviewed
金子 政時, 谷口 光代, 髙間 有紀
周産期医学 55 ( 13 ) 220 - 223 2025.12
Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:東京医学社
-
Tomiki Yuka, Taniguchi Mitsuyo, Yoshinaga Saori, Kaneko Masatoki
JOURNAL OF JAPAN HEALTH MEDICINE ASSOCIATION 34 ( 3 ) 402 - 407 2025.10
Language:Japanese Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:JAPAN HEALTH MEDICINE ASSOCIATION
This study aimed to elucidate the age groups of cervical cancer screening examinees conducted by local governments in Miyazaki Prefecture and the effects of municipal initiatives. This study included 8944 examinees [4395 in Fiscal year (FY) 2022 and 4549 in FY2023] from two cities and six towns. The number of examinations was 160 (84 in FY2022 and 76 in FY2023). The number of new examinees was 394 (89 in FY2022 and 305 in FY2023), and the median age was 60 and 23 years for all and new examinees, respectively. The municipality that implemented campus screening of cervical cancer demonstrated an increase in the number of new examinees and a significant decrease in the age of new examinees. Five municipalities conducted weekend examination (11 times in FY2022 and 13 times in FY2023), and no difference in the number of new examinees was noted between weekday and weekend examinations in all five municipalities. However, the number of new examinees was significantly higher than the number of new examinees for weekday examinations in the municipality that conducted 14 weekend examinations, including three evening examinations (total examinations : 22), and the age of the examinees tended to be younger ; although, the difference was not significant. In this municipality, the number of examinees per examination was 119.7 and 68.6 for weekend and weekday examinations, respectively. The examinees exhibited a higher age distribution than the age groups affected by cervical cancer. Initiatives are required to increase the number of examinees in younger age groups across Miyazaki Prefecture. Actively introducing weekend examinations may result in an increased number of new examinees and a decreased age of examinees.
-
Trends and issues in music therapy intervention research in neonatal intensive care units Reviewed
Oyama Yuko, Taniguchi Mitsuyo, Tanaka Michi, Kuroiwa Miyuki, Shimizu Mari, Miyamoto Yukari
( 9 ) 31 - 41 2025.3
Language:English Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution)
DOI: 10.57503/0002000167
-
特集 ローリスク妊婦ローリスク新生児のケア2025 妊娠時 妊婦健診における検体検査 Reviewed
金子 政時, 谷口 光代
周産期医学 55 ( 1 ) 32 - 34 2025.1
Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:東京医学社
-
Tsuda Honoka, Kaneko Masatoki, Tsuruta Kurumi, Yamazaki Keiko, Tanabe Ayako, Yoshinaga Saori, Taniguchi Mitsuyo, Fujii Yoshinori
JOURNAL OF JAPAN HEALTH MEDICINE ASSOCIATION 33 ( 2 ) 200 - 207 2024.7
Language:English Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:JAPAN HEALTH MEDICINE ASSOCIATION
The purpose of this study is to clarify the reality of domestic violence among pregnant women during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and its impact on their quality of life. This cross-sectional study was conducted from June 30 to November 30, 2021. Pregnant women could access our anonymous self-administered questionnaire via a QR code. Domestic violence was assessed using the Violence Against Women Screen (VAWS) instrument. The quality of life and health were evaluated using the Japanese version of the 12-item Short Form Survey (SF-12). Of the 303 pregnant women enrolled in this study, 62 (20.5%) suffered from domestic violence. In VAWS, psychological violence was the most common type at a low score, whereas physiological violence gradually became noticeable as the score increased. The frequency of women planning to continue working after delivery was significantly higher in the group without domestic violence than in the group with domestic violence. Domestic violence influenced the physical functioning of women’s quality of life, although other areas of the quality of life showed no significant differences. Furthermore, the VAWS score did not correlate with the scores of any area of SF-12. Domestic violence in pregnant women during the COVID-19 pandemic began silently without physical aggression and gradually progressed to actions with greater intensity. A system that early detects psychological violence and supports pregnant women for violence prevention must be established.
DOI: 10.20685/kenkouigaku.33.2_200
Other Link: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I033650337
MISC 【 display / non-display 】
-
宮崎県A市の子宮頸がん集団バス検診における自治体の取り組みの検証 Reviewed
富来 由華, 金子 政時, 谷口 光代, 吉永 砂織
日本健康医学会雑誌 34 ( 3 ) 326 - 327 2025.10
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:日本健康医学会
-
火山爆発を想定した災害防災訓練に参加することによる学び Reviewed
谷口 光代
日本臨床救急医学会雑誌 28 ( 2 ) 309 - 309 2025.6
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:(一社)日本臨床救急医学会
-
[フィールドこぼれ話] 結いの島で奄美分室設置10周年を迎えて Reviewed
谷口, 光代
島嶼研だより 89 9 - 9 2025.3
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:鹿児島大学
-
ミクロネシアの小島嶼での蚊幼虫生息調査について Reviewed
大塚 靖, 山本 宗立, 川西 基博, 谷口 光代
衛生動物 76 ( Suppl. ) 70 - 70 2025.3
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:日本衛生動物学会
-
モロッコにおける助産師学生を対象にした産痛緩和ケア教育前後の比較 産痛緩和ケア行動の分析 Reviewed International coauthorship
谷口 光代, 田村 康子, Milouda Chebabe, Ahmed Ouassim
グローバルヘルス合同大会プログラム・抄録集 2024 203 - 203 2024.11
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:グローバルヘルス合同大会事務局
Presentations 【 display / non-display 】
-
モロッコにおける助産師学生を対象にした産痛緩和ケア教育前後の比較 -産痛緩和ケア行動の分析- International coauthorship
谷口 光代,田村 康子,Chebabe Milouda,Ouassim Ahmed
グローバルヘルス合同大会 第39回日本国際保健医療学会学術大会 2024.11
Event date: 2024.11.16 - 2024.11.17
Language:Japanese Presentation type:Poster presentation
-
妊娠期から行う「夫婦ペアレンティング教育プログラム」が経産婦夫婦に与える効果
谷口光代 上澤悦子 木野寛子
第65回日本母性衛生学会学術集会 2024.10.19
Event date: 2024.10.18 - 2024.10.19
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
-
子育て中の母親の次子希望に影響を与える要因を明らかにするための質問紙調査
押川 美月, 金子 政時, 山崎 圭子, 松岡 あやか, 谷口 光代, ポッター 美歩
第65回日本母性衛生学会学術集会 2024.10.19
Event date: 2024.10.18 - 2024.10.19
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
-
トルコ・シリア地震派遣において分娩台を設置した分娩室兼予備手術室の活用 妊婦ケアに対する援助が安全に提供できる知識・技術の必要性
秋山 真紀子, 谷口 光代, 黒住 健人, 石川 源, 川谷 陽子
第29回日本災害医学会総会学術集会 2024.2.23
Event date: 2024.2.22 - 2024.2.24
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
-
2023 年トルコ地震に見るJDR医療チーム派遣における産科診療の現状と課題
石川 源, 高村 ゆ希, 谷口 光代, 竹田津 史野, 三浦 由紀子, 夏川 知輝, 大場 次郎, 黒住 健人
第29回日本災害医学会総会学術集会 2024.2.23
Event date: 2024.2.22 - 2024.2.24
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Grant-in-Aid for Scientific Research 【 display / non-display 】
-
ミクロネシアにおける地域住民主導による蚊媒介性感染症対策の確立
Grant number:23K25095 2024.04 - 2026.03
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
Authorship:Coinvestigator(s)
-
離島で出産する夫婦のエンパワーメントを高める健康教育プログラムの開発
Grant number:22K11048 2022.04 - 2026.03
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Authorship:Principal investigator
-
Establishment of community-led mosquito-borne infectious disease control in Micronesia
Grant number:22H03841 2022.04 - 2026.03
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Authorship:Coinvestigator(s)
-
産後うつ予防のための妊婦中からの筋力トレーニングプログラムの開発
Grant number:21K10959 2021.04 - 2025.03
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(C)
木野 寛子, 上澤 悦子, 谷口 光代
Authorship:Coinvestigator(s)
本研究の目的である、妊婦の筋肉量の妊娠中から産後の経時的変化、筋肉量と疲労度、産後うつの関連を明らかにすることについての進捗状況は、体組成計とデータ管理のためのPCを購入し、研究協力施設とデータ収集方法の調整中であり、方法が決定次第、倫理審査を進めていく予定である。妊娠中の適切なエクササイズ方法や、現在の産後うつの状況につちえは、関連の文献検討を進めている。
妊婦の筋肉量については、関連研究も進めている最中である。関連研究の結果によると、体重に対する筋肉量の割合は、妊娠末期になるに従い増加し、産後は減少する。しかし、妊娠中のエクササイズや運動の実施の有無により、やや減少率に差が見られる。産後すぐは、ほぼ全てに褥婦が軽いストレッチなどのエクササイズしかすることはできず、妊娠中のエクササイズや運動が関連していると考えられる。しかし、関連研究では限界があり、本研究で関連を調べていく予定である。
産後うつは身体的疲労と精神的疲労が複合的に要因となっている。身体的疲労には体力が関連しており、筋肉量の維持は疲労回復に効果があると考えられる。昨今の新型コロナの影響で、産後うつも増加傾向であり、早急な対応が求められている。
本研究の筋力トレーニングプログラムは、自宅でできるプログラムを考えている。筋力トレーニングは自宅で短時間の実施可能なエクササイズなため、現在のコロナ禍においても有用なエクササイズとなると考えられる。 -
モロッコにおける産痛緩和ケアに関する助産師基礎教育モデルの開発
Grant number:18K10413 2018.04 - 2025.03
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(C)
田村 康子, 谷口 光代
Authorship:Coinvestigator(s)
本研究の目的は、産痛緩和ケアに関する助産師の実践コミュニティ形成を基盤としながら、産痛緩和ケア実践能力養成に関する基礎助産師教育における教育モデル開発を行うことである。令和3年度においては、モロッコ国セタット県にあるハッサン1世大学の助産学科の教員と毎月1回程度のオンライン会議を重ねた(12回会議実施)。3年間の助産学科での教育カリキュラムの中で、どのように産痛緩和ケアに関する学習を配置していくか、どのように教育するかについて検討した。加えて、実習施設の実習指導者は学生が実習を通して産痛緩和ケアを学ぶ上で、実践コミュニティの一員となるが、その指導者と教員との実習に関する連携がシステムとしてないことが課題としてあることから、実習指導者を対象とした産痛緩和ケア技術に関する技術習得支援も含めた実習指導者会の企画も検討した。
検討の末、助産師学生へは3年生前期に講義演習し、前期の分娩介助実習、後期の分娩介助実習にてケア習得について効果を明らかにすることとした。また3年生の分娩介助実習に先立ち、臨床指導者を対象とした指導者会を実施し、先行研究で開発した産痛緩和ケア教育プログラムにて習得を支援することとした。助産師学生と臨床指導者それぞれの取り組みについて、兵庫医療大学の研究倫理委員会の承認を受けた(令和3年10月)。モロッコ側の予定変更があり、3年生後期となる令和3年度3月21日に3年生助産師学生33名、臨床指導者5名を対象に産痛緩和ケアに関する講義と演習を行った。教育プログラム実施前後のケアに対する認識と実践の変化について、先行研究で開発した尺度を用いた測定を行っている。3年生後期の分娩介助実習が令和4年度4月に入ってからであり、実習後の尺度への入力とインタビュー実施(オンライン)は令和4年5月に実施する予定である。