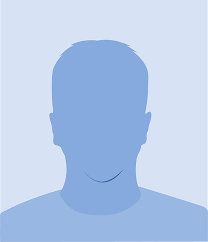|
所属 |
医学部 看護学科 子育て世代・子ども健康看護科学講座 |
|
職名 |
教授 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
学位 【 表示 / 非表示 】
-
看護学博士 ( 2012年3月 聖路加看護大学 )
-
修士(看護学) ( 2002年3月 聖路加看護大学 )
-
看護学士 ( 1985年3月 千葉大学 )
学歴 【 表示 / 非表示 】
-
聖路加看護大学 看護学研究科 小児看護学
- 2012年3月
国名:日本国
-
聖路加看護大学 看護学研究科 小児看護学
- 2002年3月
国名:日本国
-
千葉大学 看護学部 看護学科
- 1985年3月
国名:日本国
所属学協会 【 表示 / 非表示 】
-
日本小児看護学会
1990年4月 - 現在
-
日本遺伝看護学会
2008年7月 - 現在
-
日本小児保健協会
1990年4月 - 現在
-
日本看護管理学会
1997年4月 - 現在
-
日本看護科学学会
2002年4月 - 現在
論文 【 表示 / 非表示 】
-
ターナー女児の健康管理に関する親から子どもへの コミュニケーションの実態 査読あり
荒武 亜紀, 野間口 千香穂, 野末 明希, 矢野 朋実, 狩集 綾子, 澤田 浩武
日本遺伝看護学会誌 22 ( 0 ) 34 - 42 2024年4月
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本遺伝看護学会
<b>目的</b>:ターナー女児の健康管理に関する親から子どもへのコミュニケーションの実態を明らかにする。<b>方法</b>:国内のターナー女児を診療するTrace The Turner Study Groupに所属する小児科医が担当する小児科外来通院中のターナー女児の保護者および国内のターナー家族会に登録している小児科外来通院中のターナー女児の保護者に研究者らが作成した無記名自記式質問紙調査票の配布を依頼し、郵送による回収を行った。調査内容は、回答者の属性、子どもの年齢、診断年齢、治療の状況、ターナー症候群に関する情報入手の状況、体質や治療・健康管理に関する13項目の知識の有無、子どもに話しているか否か、子どもに話した人、子どもに話すうえでの困りごとに関することであり、記述統計にて分析した。<b>結果</b>:対象者134名に配布し48名から回答が得られ、回収率は35.8%であった。ターナー症候群の体質や治療・健康管理に関する13項目中いずれかの項目を子どもに話していると回答したのは、48名中41名(85.4%)であった。ターナー症候群の体質や治療・健康管理に関する13項目中10項目を8割以上が「知識あり」と回答していた。「自然妊娠しづらい」ことは、9割以上が「知識あり」と回答していたが、子どもに話していたのは4割程度であった。年齢区分別では、13 ~15歳ではおよそ7割程度が話していたが、年齢が上がるにつれて話している割合が高いわけではなかった。子どもに話していた多くは母親、医師であった。子どもに話すうえでの困りごとには、「わかりやすく話すことが難しい」19名(39.6%)、次いで「どう受け取ったのかわからない」18名(37.5%)、「どのように話したらよいかわからない」10名(20.8%)ことを挙げていた。<b>考察</b>:子ども自身が日常生活のなかで直接的に体験していることは話題にしやすく、一方で、予防として健康管理が必要なこと、子どもが直面していないことは話題にされないことや話題になりにくいことが考えられた。
-
学会誌の発展に向けた協働: 投稿者・査読者・編集委員会の連携による今後の展望 査読あり
辻 恵子, 荒木 奈緒, 岡永 真由美, 石橋 みちる, 中村 由唯, 村上 京子, 矢野 朋実, 野間口 千香穂
日本遺伝看護学会誌 23 7 - 12 2025年5月
担当区分:最終著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
看護技術習得過程における左手利き看護師の方略 査読あり
川西 幸広, 野間口 千香穂, 澤田 浩武
日本看護技術学会誌 23 ( 0 ) 150 - 157 2024年12月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本看護技術学会
目的:看護技術習得過程における左手利き看護師の方略を明らかにする. <br> 方法:臨床経験年数3年以上の左手利き看護師4名を対象に, 半構造化面接を行い, 質的記述的に分析した. <br> 結果:知る段階では, 【実演を模倣する】【実演者に操作する手の確認を行う】, 身につける段階では, 【操作する手を自分で決める】【周囲の反応に応えようとする】【左手で操作するための工夫をする】こと, 幼少期から【自然に身についている習得法を応用する】ことを基盤として看護技術習得を行っていた. <br> 結論:左手利きの看護師は, 知る段階では操作する手の確認ができず, 身につける段階で両方の手を試し, 安全性, 巧緻性, 効率性, 他者への影響などの要因に基づいて実践する手を決め, 左手で実践する場合の工夫を行っていた.
-
南九州地方1県の漁村における高齢女性の育児経験者が語る母親としての育児を巡る体験 査読あり
荒武亜紀、野間口千香穂、松岡あやか
南九州看護研究誌 20 ( 1 ) 27 - 36 2022年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:宮崎大学医学部看護学科
Child care in local communities could be further supported with suggestions on child- rearing and child-rearing environments for the society of today. Accordingly, the objective of this study is to elucidate narratives on child-rearing and the child-rearing environment from elderly women’s with personal experience of child-rearing in fishing villages. The semi-structured interviews with nine women aged 80 or above who lived in fishing-industry-dominated areas and had experience of child-rearing provided data for analysis. The results of the analysis indicated six categories: “neighborhood ties”, “responsibilities of family heads for safeguarding children and the family business”, “cultivate child-rearing ability through caring for children from a very early age”, “incorporating child-rearing into daily activities”, “explaining local community rules to children”, and “promoting and preserving child health.” “Neighborhood ties” had a dual significance in the child-rearing environment; mothers were supported in their parenting role at the same time as being in a setting where child-rearing ability could be cultivated through experience.
Narratives focusing on the role of the mother emphasized the progressive socialization of children and the support for child care in the local community provided by people in the neighborhood. Maternal child-caring became a natural act in the mother’s own upbringing, based on frequent experiences of regularly looking after younger siblings as a part of life from a very young age. Accordingly, this analysis suggests that child care needs to be implemented as a function of the local community. Furthermore, the strengths and nature of the relevant local community can underpin a community-based integrated care system capable of responding to local diversity. We also suggest that the reinforcement and collaboration entailed in such a system are vital for child care in local communities. -
産後の疲労感に対するセルフモニタリングが セルフケア行動を促進した一事例 査読あり
林佳子、野間口千香穂、山﨑圭子
南九州看護研究誌 20 ( 1 ) 18 - 26 2022年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:宮崎大学医学部看護学科
産後の母親に,産後のホルモンの変化に伴う心身の症状と産後の疲労感を測定できる産後の疲労感尺度Ver.1について情報提供を行ったところ,産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行なった事例を経験した。本稿では,セルフモニタリングに至った状況と,セルフモニタリング後の疲労感の自覚と行動の変化について報告する。
研究方法は,自記式質問紙調査(産後の疲労感尺度Ver.1,エジンバラ産後うつ病質問票)と,退院後から産後1か月健診時までの期間で,産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行おうと思った時の状況とセルフモニタリング後の疲労感の自覚と行動の変化について半構造化面接を行った。
分析の結果,44のコードが抽出され,14のサブカテゴリ,5のカテゴリに集約された。「余裕の無さ」と「苛立ち」は,産後の疲労感の増強した時の指標となることが示唆された。産後の疲労感尺度を用いて客観的にセルフモニタリングすることで,現在の自分の心身の状態に関心がむけられ,余裕をもたらすための援助要請や自分の疲労状態に応じたセルフケア行動につながった。
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
プライマリ・ケア看護学 小児期から成人期への移行支援
野間口 千香穂( 担当: 共著 , 範囲: 小児期発症慢性疾患を有する子どもと家族への看護)
南山堂 2023年4月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
看護実践のための根拠がわかる小児看護技術 第3版
添田啓子、三宅玉恵、鈴木千衣、野間口千香穂、他( 担当: 分担執筆 , 範囲: 第Ⅳ章 日常生活援助にかかわる看護技術8.環境の調整)
メジカルフレンド社 2022年12月
記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
-
小児看護と看護倫理
松岡真里編著, 古橋知子、笹月桃子、竹ノ内直子他( 担当: 分担執筆)
へるす出版 2020年4月
総ページ数:214 担当ページ:208-214 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
西垣 昌和, 渡邉 淳, 中込 さと子( 担当: 分担執筆 , 範囲: 小児期発症する遺伝性疾患を有する子ども・家族への看護)
羊土社 2019年2月
総ページ数:177 担当ページ:98-111 記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
遺伝看護の展開について、小児期発症する遺伝性疾患を有する子ども・家族への看護として、疾患の多様性と継承性の特徴と成り立ちや治療、子どもと家族の心理社会的側面や社会の状況について概説し、遺伝看護の視点について提示した。
-
有森 直子, 溝口 満子, 井ノ上 逸朗 他( 担当: 分担執筆 , 範囲: 先天代謝異常症)
医歯薬出版 2018年2月
総ページ数:247 担当ページ:88-100 記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
小児期の遺伝/ゲノム看護について、先天代謝異常症の場合に遺伝性疾患であるがゆえに起こり得る状況とそれに対する看護を概説し、フェニールケトン尿症の事例をもとにした看護の展開を提示した。
MISC 【 表示 / 非表示 】
-
野間口千香穂
小児看護 42 ( 13 ) 1614 - 1617 2019年12月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:へるす出版
慢性疾患のある子どもの自立支援の特集号での執筆である。慢性疾患児とその家族の特徴と疾患による発達や自立への影響について、これまでの知見を整理し、筆者らが開発した慢性疾患児の自立に向けた療養支援のための自立度確認シートの基盤となっている考え方を概説した。
-
混合病棟における10代患者の看護
野間口千香穂
小児看護 30 ( 10 ) 1388 - 1394 2007年9月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 出版者・発行元:へるす出版
-
思春期 招待あり
野間口 千香穂
小児看護 27 ( 5 ) 542 - 547 2004年4月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:へるす出版
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
妊娠初期における妊婦の抑うつリスクに影響を与える要因-EPDSを用いた検討-
上田明佳,野間口千香穂
第65回 日本母性衛生学会総会・学術集会 2024年10月18日
開催年月日: 2024年10月18日 - 2024年10月19日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
-
3歳未満の子どもをもつ父親の育児に対する考えと行動に関する質的研究
谷山碧南,野間口千香穂
第65回 日本母性衛生学会総会・学術集会 2024年10月19日
開催年月日: 2024年10月18日 - 2024年10月19日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
-
育児疑似体験学習の成果とカリキュラム改訂に向けた検討
狩集綾子,野間口千香穂
第23回 九州・沖縄小児看護教育研究会 2023年8月19日
開催年月日: 2023年8月19日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
-
小児慢性疾患児の療養・生活支援:就園と自立支援について 招待あり
野間口千香穂
第33回全国穂意見保健研究大会 2023年2月5日
開催年月日: 2023年2月5日
記述言語:日本語 会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)
-
NICUで死別を経験した母親の子どもに対する認識と行動
奈須まどか、野間口千香穂
第31回日本新生児看護学会学術集会 2022年11月26日
開催年月日: 2022年11月25日 - 2022年11月26日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
慢性疾患児の自立に向けた療養支援モデルの外来看護実践への適用と評価
研究課題/領域番号:25K14091 2025年04月 - 2028年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
先天性心疾患児の母親へのレジリエンス促進支援モデルに基づいた介入プログラムの開発
研究課題/領域番号:24K13888 2024年04月 - 2028年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(C)
担当区分:研究分担者
-
実践的看護臨床薬理学教育モデル(iDrug)に基づいた新たな教育システムの開発
研究課題/領域番号:23K21531 2024年04月 - 2025年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
実践的看護臨床薬理学教育モデル(iDrug)に基づいた新たな教育システムの開発
研究課題/領域番号:21H03223 2021年04月 - 2025年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
柳田 俊彦、
担当区分:研究分担者
-
小児期を通して行う慢性疾患児の自立に向けた看護療養支援システムの構築
研究課題/領域番号:18H03096 2018年 - 2023年03月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
担当区分:研究代表者
本研究の最終目的は、小児期を通して行う慢性疾患児の自立に向けた療養支援体制を構築することである。
今回実施する研究では、申請者らが開発した慢性疾患児の自立に向けた療養支援モデルを活用した慢性疾患児の自立に向けた看護職による療養支援システムを構築することを目的として、(1)療養支援モデル活用に必要な看護職のための教育教材作成と療養支援モデル活用ガイドの作成、(2)慢性疾患児の自立と家族の自立支援に役立つ患児・家族向けのツールの作成(3)療養支援モデル活用のための看護職に対
する教育研修の実施と評価を行うことによって、施設を越えた療養支援モデルの実用化を図り、小児期を通して行う慢性疾患児の自立に向けた療養支援を推進する基盤体制をつくる。
その他研究活動 【 表示 / 非表示 】
-
厚労科研「小児慢性特定疾病児童等の自立支援の充実に資する研究:分担研究(仁尾かおり)」
2021年04月 - 現在
具体的な情報収集に努め、(1)好事例集を発行することにより情報共有し、(2)全国実施状況調査の解析を継続して行い経年的変化を把握し課題を抽出し、研究のなかで明らかになった小慢児童とその家族のニーズに即した新規研究も随時追加して、(3)2018-2019年度に行った自立支援員による相談対応、保健所の役割、保育所・幼稚園への就園、就学・学習支援、就労支援、きょうだい児支援、移行期支援についての実態調査および相談事例のモデル対応集などに基づいて、すべての情報をまとめて、自立支援員のための自立支援事業実施手引きや自立支援員研修教材の作成を目指し、今後の自立支援事業の発展に貢献できることを目指している。
-
厚労科研「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の発展に資する研究:分担研究(及川郁子)」
2020年04月 - 2021年03月
-
厚労科研「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の発展に資する研究:分担研究(及川郁子)」
2019年04月 - 2020年03月
-
厚労科研「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の発展に資する研究:分担研究(及川郁子)」
2018年04月 - 2019年03月
-
厚労科研「慢性疾患に罹患している児の社会生活支援ならびに療育生活支援に関する実態調査およびそれらの施策の充実に関する研究:分担研究(及川郁子)」
2015年04月 - 2016年03月
小児看護専門看護師の協力を得て、慢性疾患児の自立に向けた療養支援モデルを開発した。療養支援モデルは乳幼児期から思春期まで発達段階にあった5つの支援領域について、その確認シートとケアモデルを組み合わせたものであり、研究の成果として療養支援ガイドを作成した。
研究・技術シーズ 【 表示 / 非表示 】
-
慢性疾患児の自立に向けた療養支援モデルに関する研究

長期的障がいや慢性疾患をもつ子どもの家族支援に関する研究
遺伝性疾患を有する家族間コミュニケーションに関する研究ホームページ: 宮崎大学医学部看護学科 小児看護学領域ホームページ
技術相談に応じられる関連分野:病気をもつ子どもの療養支援、家族支援
メッセージ:慢性疾患児の療養支援や子育て支援は、地域での包括的な支援が重要です。このような包括的支援や急速に拡大する遺伝医療の中で当事者のへの支援など、関心がある方はぜひご連絡ください。
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
日本小児看護学会 理事長
2023年6月 - 現在
団体区分:学協会
-
社会保障審議会専門委員 社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病児への支援の在り方に関する専門委員会
2022年6月 - 現在
団体区分:政府
-
日本遺伝看護学会 学会誌編集委員会
2022年5月 - 現在
団体区分:学協会
-
日本看護科学学会 表彰論文選考委員会委員
2019年7月 - 現在
団体区分:学協会
-
日本看護科学学会 代議員
2019年2月 - 現在
団体区分:学協会