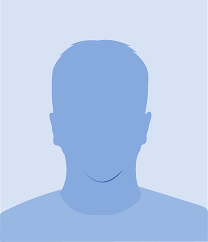|
所属 |
医学部 看護学科 統合臨床看護科学講座 |
|
職名 |
教授 |
|
外部リンク |
|
|
関連SDGs |
論文 【 表示 / 非表示 】
-
巻頭言 査読あり
柳田 俊彦
エキスパートナース 41 ( 6 ) 3 - 3 2025年4月
-
Maruta T., Kouroki S., Kurogi M., Hidaka K., Koshida T., Miura A., Nakagawa H., Yanagita T., Takeya R., Tsuneyoshi I.
Journal of Neuroscience Research 102 ( 10 ) e25386 2024年10月
記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Journal of Neuroscience Research
Voltage-gated sodium channels, including NaV1.7, NaV1.8, and NaV1.9, play important roles in pain transmission and chronic pain development. However, the specific mechanisms of their action remain unclear, highlighting the need for in vivo stimulation studies of these channels. Optogenetics, a novel technique for targeting the activation or inhibition of specific neural circuits using light, offers a promising solution. In our previous study, we used optogenetics to selectively excite NaV1.7-expressing neurons in the dorsal root ganglion of mice to induce nocifensive behavior. Here, we further characterize the impact of nocifensive behavior by activation of NaV1.7, NaV1.8, or NaV1.9-expressing neurons. Using CRISPR/Cas9-mediated homologous recombination, NaV1.7–iCre, NaV1.8–iCre, or NaV1.9–iCre mice expressing iCre recombinase under the control of the endogenous NaV1.7, NaV1.8, or NaV1.9 gene promoter were produced. These mice were then bred with channelrhodopsin-2 (ChR2) Cre–reporter Ai32 mice to obtain NaV1.7–ChR2, NaV1.8–ChR2, or NaV1.9–ChR2 mice. Blue light exposure triggered paw withdrawal in all mice, with the strongest response in NaV1.8–ChR2 mice. These light sensitivity differences observed across NaV1.x–ChR2 mice may be dependent on ChR2 expression or reflect the inherent disparities in their pain transmission roles. In conclusion, we have generated noninvasive pain models, with optically activated peripheral nociceptors. We believe that studies using optogenetics will further elucidate the role of sodium channel subtypes in pain transmission.
DOI: 10.1002/jnr.25386
-
Assessment of insulin balls: A scoping review
Nakamura Sayuri, Kageura Naoko, Oe Makoto, Matsui Yuko, Horiguchi Tomomi, Ueda Terumi, Seto Natsuko, Yanagita Toshihiko, Sugama Junko
Journal of International Nursing Research 3 ( 1 ) e2023-0010 - e2023-0010 2024年2月
記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本看護研究学会
Insulin balls are subcutaneous induration caused by amyloid deposition due to repeated insulin injections to the same site, and subcutaneous injections in this area cause poor glycemic control. Therefore, it is important to assess the site for insulin balls and change the injection site at an early stage, but the assessment method remains unclear. Therefore, we aimed to clarify the available methods for insulin ball assessment. Using the scoping review method, we searched Japanese and English literature from January 1964 to November 2022 using the keywords "insulin ball" and "assessment" and included those that met the selection criteria. Database searches were conducted in Japan Abstracts Society, PubMed, Scopus, and CINAHL. The number of adopted studies regarding insulin ball assessment was 11. Palpation and visual examination were the assessment methods used in all studies. Blood tests and ultrasonography were both performed in nine articles, magnetic resonance imaging (MRI) was performed in five articles, and computed tomography (CT) was performed in four articles. There were two types of insulin balls: palpable and nonpalpable. A paper reporting that nonpalpable insulin balls can be detected by ultrasonography was noted. In addition to palpation and visual examination, imaging tests such as ultrasonography, MRI, and CT are necessary because some insulin balls cannot be palpated. This study suggested that incorporating ultrasonography in addition to palpation and visual examination may be useful as a screening tool for the early detection of insulin balls. We now need to validate the accuracy of the assessment by ultrasonography.
-
柳田 俊彦, 笹栗 俊之
日本薬理学雑誌 158 ( 2 ) 111 - 111 2023年
担当区分:筆頭著者, 責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:公益社団法人 日本薬理学会
DOI: 10.1254/fpj.23002
-
Yanagita T.
Folia Pharmacologica Japonica 158 ( 2 ) 119 - 127 2023年
担当区分:筆頭著者, 責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:Folia Pharmacologica Japonica
Active learning in pharmacology education “pharmacology role-play,” in which students pretend to be health professionals and patients and explain diseases and drug treatments. Because pharmacology role-play is based on cases presented in advance and active learning through communication, named Case & Communication based approach (C&C approach). Pharmacology role-play was started in 2010 at the University of Miyazaki, it has been shared by 28 schools in 4 faculties of medicine, pharmacy, dentistry, and nursing (23 medical schools, 1 pharmaceutical school, 2 dental schools, and 2 nursing universities) over the 13 years until 2022. Although it is a common program, it is implemented with diversity while devoting various ingenuity according to the characteristics of the University. Pharmacology role-play is effective in (1) understanding of medical treatment, (2) understanding patient’s feelings, (3) improvement of mental attitude and motivation as health professionals (4) positive influence upon study attitude, regardless of universities that conducted the pharmacology role-play. Various efforts include combining with Personal Drugs, developing interprofessional education through joint role-playing by medical students and nursing students, and developing Oriental medicine education through the cases including Kampo medicine. In addition, there are online lectures in response to the Covid-19, and a joint implementation of two universities, all of which are highly effective. The advantage of the multi-institution common program is that a lot of information can be obtained at once, and it is easy to quickly reflect successful ideas. The flexibility and high resilience that can flexibly change the implementation method (face-to-face/remote) according to the situation are also great strengths.
DOI: 10.1254/fpj.22111
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
武田 泰生, 齋藤 秀之 (応用薬理学), 伊東 弘樹, 池田 龍二 (医療系薬学), 柳田 俊彦( 担当: 単著)
南山堂 2023年 ( ISBN:9784525500719 )
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
臨床麻酔インスリンと記憶:海馬におけるその働きと治療へのアプローチ
柳田俊彦、丸田豊明、根本隆行( 担当: 共著)
真興交易 2020年3月
記述言語:日本語
MISC 【 表示 / 非表示 】
-
連載 事例で解説!「この場面」の"なぜ?"がわかるくすりの知識(第24回)(最終回)アトピー性皮膚炎の患者への投薬 査読あり
柳田 俊彦
エキスパートナース 41 ( 3 ) 95 - 110 2025年2月
-
連載 事例で解説!「この場面」の"なぜ?"がわかるくすりの知識(第23回)認知症(アルツハイマー型認知症)患者への投薬 査読あり
柳田 俊彦
エキスパートナース 41 ( 2 ) 79 - 92 2025年1月
-
連載 事例で解説!「この場面」の"なぜ?"がわかるくすりの知識(第22回)痛みを訴える患者へのさまざまな投薬 査読あり
柳田 俊彦
エキスパートナース 41 ( 1 ) 113 - 128 2024年12月
-
連載 事例で解説!「この場面」の"なぜ?"がわかるくすりの知識(第20回)腎機能が低下している患者への投薬 査読あり
柳田 俊彦
エキスパートナース 40 ( 13 ) 103 - 122 2024年10月
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
ロールプレイのすゝめ 〜学生主体型 ”医師-患者ロールプレイ” による実践的薬物治療教育の有効性〜(薬理学教育シンポジウム) 次世代の医学部薬理学実習の提案
柳田俊彦
第93回 日本薬理学会年会
開催年月日: 2020年3月16日 - 2020年3月18日
記述言語:日本語 会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)
-
看護における臨床薬理学教育 〜 漢方教育の充実に向けて 〜 招待あり
柳田俊彦
第12回 看護学系漢方教育研究会
開催年月日: 2019年9月28日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(招待・特別)
-
薬理学ロールプレイを活用した 漢方医学教育の試み (ランチョンセミナー) 招待あり
柳田俊彦
第51回 日本医学教育学会大会
開催年月日: 2019年9月28日
記述言語:日本語 会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
-
看護の視点と薬物治療 〜 看護が変える・看護が変わる 〜(教育講演)
柳田俊彦
看護薬理学カンファレンス2019 in 大阪
開催年月日: 2019年3月16日
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(招待・特別)
-
看護師による与薬の質と安全性の向上を目指して- integrated Drug (iDrug)と与薬のしおり- (シンポジウム)与薬の実践者である看護師に必要な薬理学教育とは- 看護師・薬剤師・医師の立場から -
柳田俊彦, 池田龍二, 平原康寿
第92回日本薬理学会年会
開催年月日: 2019年3月14日 - 2019年3月16日
記述言語:日本語 会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)
受賞 【 表示 / 非表示 】
-
加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 研究助成金
2002年5月 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団
柳田俊彦
受賞区分:国内外の国際的学術賞 受賞国:日本国
-
日本薬理学会年会 優秀発表賞
2002年3月 日本薬理学会
柳田 俊彦
受賞区分:国内学会・会議・シンポジウム等の賞 受賞国:日本国
-
金原一郎記念医学医療振興財団 研究助成金
2000年9月 金原一郎記念医学医療振興財団
柳田俊彦
受賞区分:出版社・新聞社・財団等の賞 受賞国:日本国
-
9th International Symposium on Chromaffin Cell Biology Young Investigator Award
1997年5月 International Symposium on Chromaffin Cell Biology
Toshihiko Yanagita
受賞区分:国際学会・会議・シンポジウム等の賞 受賞国:日本国
科研費(文科省・学振・厚労省)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
看護のリアリティとバーチャル融合型シミュレーションプラットフォームの構築
研究課題/領域番号:23K27870 2024年04月 - 2027年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
実践的看護臨床薬理学教育モデル(iDrug)に基づいた新たな教育システムの開発
研究課題/領域番号:23K21531 2024年04月 - 2025年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基金 基盤研究(B)
担当区分:研究代表者
-
看護のリアリティとバーチャル融合型シミュレーションプラットフォームの構築
研究課題/領域番号:23H03180 2023年04月 - 2027年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
実践的看護臨床薬理学教育モデル(iDrug)に基づいた新たな教育システムの開発
研究課題/領域番号:21H03223 2021年04月 - 2025年03月
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
担当区分:研究代表者
-
神経細胞のインスリン抵抗性:改善因子・増悪因子の同定とその作用機序の解明
研究課題/領域番号:24500442 2012年04月 - 2015年03月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
神経細胞のインスリン抵抗性:改善因子・増悪因子の同定とその作用機序の解明
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
脳内ニコチン受容体活性化によって起こる受容体構造変化の可視化による解析
2007年03月 - 2010年03月
民間財団等 財団法人喫煙科学研究財団 研究助成金
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
脳内ニコチン受容体活性化によって起こるニコチン受容体の構造変化を可視化するとともに、その機能変化を解析する0
-
アドレノメデュリンと関連ペプチドの実用化のための基盤研究
2005年04月 - 2008年03月
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成17年度 産業技術研究助成事業費助成金
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
アドレノメデュリンと関連ペプチドの臨床応用に向けての基盤研究
-
妊娠子宮におけるアドレノメデュリンの発現調節機構と子宮収縮抑制機序の解明
2002年04月 - 2003年03月
民間財団等 第13回 加藤記念研究助成金
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
妊娠子宮におけるアドレノメデュリンの発現調節機構と子宮収縮抑制機序について解析し、臨床応用の可能性を検討する。
-
MAPカイネースによる電位依存性Naチャネルの細胞膜発現調節機構
2000年09月 - 2001年03月
民間財団等 金原一郎記念医学医療振興財団 第15回基礎医学医療研究助成金
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
MAPカイネースによる電位依存性Naチャネルの細胞膜発現調節機構について解析する
寄附金・講座・研究部門 【 表示 / 非表示 】
-
看護学科研究奨学金(柳田俊彦)(一般社団法人日本漢方教育振興財団)
寄附者名称:一般社団法人日本漢方医学教育振興財団 2019年11月
-
看護学科研究奨学金(柳田俊彦)一般社団法人日本漢方教育振興財団
2019年01月